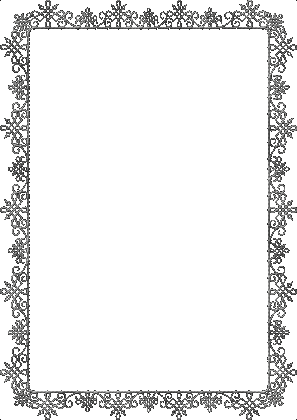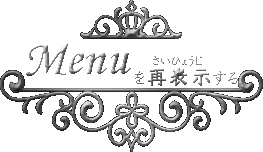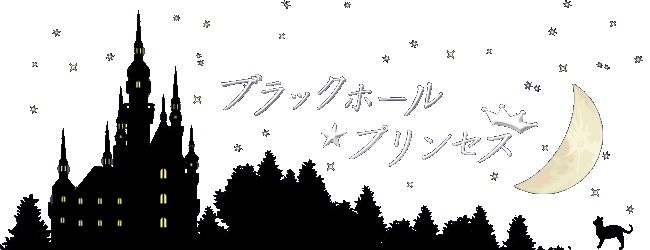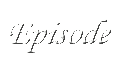|
第1話:異世界の美姫が手招きする
これは、俺のリアル中二時代の物語。
“彼女”と、そして、彼女の住む“彼の世界”との邂逅の物語だ。
それは何の前触れもなく突然に、俺の日常を歪ませて現れた。
 「やっぱさー、女も男も結局は“眉毛”だと思うわけさ。眉毛、超重要だぞ。マジで」
なんの変わり映えもない、中学二年の春の、いつもの学校からの帰り道。俺は折に触れては力説している“顔のパーツにおける眉の重要性”について、この時も熱く語っていた。
「何でだよ。百歩譲って“まつ毛”ならアリでも“眉毛”は100%ナイわ」
「そっちこそ何でだよ。眉毛一つで顔の印象ガラッと変わるぜ。今は男子でも眉の手入れに気を使う時代だって知んねーのかよ?」
俺が眉毛に注目するようになったのは、近所の何となく野暮ったかったお姉さんが女子大生になった途端、急に垢抜けて、しかもそんな印象の変化の最大要因が眉の形の変化であることに気づいてしまってからだった。
実際、日本人は遅くとも平安時代から眉を手入れし自分の理想の形に“作る”ということをしてきたし、現代でも『眉の形は時代の流行を映す鏡』などと言われている。“眉の形”が見る者の印象を左右するということに、この世の何割かの人間は既に気づいているのだ。
だから俺も事あるごとに、そんな眉毛の重要性を周りに説いて聞かせているのだが、何故だかいつも賛同してくれる人間はほとんどいない。未だに解せぬ世界の謎の一つだ。
「いや、知んねーし。つーか、お前のそのニッチにもほどがある萌えツボだけはどうしても理解できんわ」
「いやいや、萌えてはいねーよ!?俺はただ、注目すべきポイントとしてだな……」
「あ、そだ。俺、今日、本屋寄ってくんだった。欲しかった仏像写真集が入荷すんだわ。じゃ、また明日なっ」
人の好みを一方的に否定しておきながら、俺の数年来の友人・新 朝翔はさっさと曲がり角の向こうへ消えてしまった。
「……って、おいコラ、新っ!お前のシュミだって充分ニッチじゃねーかよっ!」
怒鳴ったところで返事が来るわけでもなく、俺は舌打ちしながら視線を元に戻した…………ところで、異変に気づいた。
「………………っ?……???」
人間というものは真に奇妙なモノに出くわした時、何の言葉も頭に浮かばず、ただ“ぽかん”と口を開けて見ていることしかできないものなのだと、俺はこの時初めて知った。
それは、自分の目がおかしくなったのかと疑うような光景だった。
まるで“周囲の景色を360度プリントした布”を、“肉まんの上部にある模様”のように真ん中からつまんでひねって絞ったような光景、とでも言ったら良いのか……ある一点を中心に、空間が歪んでいた。そしてその歪みの中心からは、明らかに人間の手と思しきモノが突き出していた。
透明感のある白い肌に、桜貝のような爪、華奢な印象の手指のソレは、まるで手招きでもしているかのように、ひらひらと上下していた。
(え……これって、もしかして俺を呼んでんのか……?)
一見ホラーな状況にも関わらず、好奇心の方が勝ってしまい、俺はおそるおそるその“手”に近づいていった。
歪んだ足場によろめきながら、やっとその“手”にたどり着き、指先にそっと触れた途端、“手”は見た目の印象からは想像だにしなかった素早さと力強さで俺の手を引っつかんできた。
「ひ…………ッ!」
思わず悲鳴を上げて足を踏ん張ろうとするが、歪んだ空間では思うように踏ん張れない。俺はそのまま歪みの中心に無理矢理引きずり込まれた。
そこから先は、ちょっとした阿鼻叫喚の世界だった。
何も見えない闇の中、自分の身体が得体の知れない力により引っ張られ、あり得ないほどタテ長に細く引き伸ばされ、狭い管の中を強引に通らされているような感覚だった。ひどい後悔と恐怖の中、身体中から今まで出たこともないような汗がどっと噴き出る。
ほんの数分だったのか、それとも数十時間だったのか、時間の感覚も失われた謎の暗黒空間は、唐突に終わりを告げた。
狭い穴から“すぽん”と引っ張り出されるように、俺はその世界へ引っ張り出された。
暗闇から光の中へ急に戻された俺の目が、その世界で最初に認識したものは……
「ま……眉毛……?眉毛、なのか!?何だ、この超絶美麗な眉毛はっ!?」
細過ぎず、太過ぎず、人工的に描いてあるわけではなく、かと言って全く手入れがされていないわけでもない、ナチュラルでありながら絶妙に凛々しく、かつ優美に整った理想の眉毛がそこにあった。
思わず出てしまった声に反応したのか、目の前でその美麗眉毛がぴくり、と動く。
眉毛からその下にある瞳へ、さらにその下にある唇や首や胴体へと視線を移していった時、俺はとある事実に気づき、愕然とした。
(俺……女子と手ぇつないでるじゃん!)
まるでフォークダンスを踊っている途中で時間を止めたかのように、俺は女子と向かい合い、片手と片手を握り合ってその場に立っていた。しかも相手はただの女子ではない。
雪のような白い肌に、豊かに波打つ艶やかな黒髪、宝石のように澄んだ輝きを持つ碧い瞳、そして、リアルでは文化祭の劇でしかお目にかかったことのないような、袖とスカートがふわりとふくらんだ豪華なドレス……。
(……姫じゃん。これ、どう見ても姫様じゃん。それもかなりの美少女じゃん……)
おとぎ話の白雪姫を彷彿とさせるその美姫は、こちらをじっと見つめて何度か瞬きした後、俺の手をぱっと離し、興奮した顔で隣にいた背の高い男と手を叩き合った。はしゃいだ声で何か言っているが、その言葉は今までに聞いたことのない言語で、俺には彼女が何を言っているのかさっぱり理解できなかった。
(……うん。これは、アレだな。『やりましたわ!異世界からの勇者召喚に成功しましたわ!』みたいな感じだろ。参ったな。まさかマジでこんな日が来るとは……)
これまでの人生において何度か夢想してみないではなかったシチュエーションそのままの事態に、俺は現状をあっさり受け入れ、にんまりしながら辺りを見渡してみた。
俺の“召喚”された場所は、大きな宮殿か神殿の中庭のような場所だった。足元には様々な色をした小さなタイルが敷きつめられて何かの模様を描いており、その外側には、電信柱のように屋外に突き立つ白い柱の並ぶ芝生、さらにその向こうには建物らしきものが見える。
目の前にはこの世界の人間と思しき人物が二人。一人は、布地をたっぷり使ったふんわりシルエットのドレスに、頭と腰には真紅のリボン、首元には虹色の宝石と金細工のチョーカーという姿の白雪姫風美少女。もう一人は、古代ローマ人の服装のようなゆったりした衣服に金糸の刺繍がたくさん施された、いかにも“大神官”といった姿の若い男だった。
二人は俺を無視してひとしきりはしゃぎ合った後、思い出したようにこちらに向き直り、何かを話し出した。おそらく俺とコミュニケーションをとろうとしていたのだろうが、ジェスチャーらしきものを交えて必死に話しかけられても、俺の目には何か不思議な踊りでも踊っているようにしか見えなかった。
「いや、あのー……さっぱ分かんないんスけど……。何であらかじめ、言葉が通じる魔法みたいなのとか、用意しておかないんスか?」
俺の言葉に、段取りの悪い二人は「やっぱりこれではダメだ」とようやく気づいたのか、顔を見合わせ、深刻そうに何事か相談し始める。やがて何らかの結論に達したのか、例の美姫が隣の男に向かって大きくうなずいた……と思ったら、一瞬にしてその場から消滅した。
「……は!?……えっ、ちょ……っ、消えたけどっ!?」
思わずその場に残された男へ向けて叫ぶ。言葉は通じなくてもニュアンスは伝わったのか、男は「まぁ落ち着けや」とでも言うように笑って手をヒラヒラさせた。
コミュニケーション不可能な相手とふたりきりで残されること数分、消えた時と同じように唐突に、例の美姫が出現した。それもただ現れただけではなく、もう一人増えている。美姫に手を引かれ共に出現したのは、赤ずきん風のえんじ色フードの下から長い茶髪の三つ編みをのぞかせた、魔法使いか何かでもやっていそうな雰囲気の少女だった。
少女は例の美姫と一言二言しゃべった後、俺の方へ向かってきた。そしておもむろに首にかけていたペンダントを外し、その飾りの先端を俺の額に当てる。
鍵をモチーフにしたような金の透かし彫りに虹色の宝石がはまったそのペンダントが俺の皮膚に触れた瞬間、全身を電流のようなしびれと焼けるような熱さが駆けめぐった。
「は……!?何でいきなり攻撃してくるんだよ……っ!」
てっきり攻撃魔法か何かでも喰らわされたのかと思い、俺は抗議の声を上げた。
「失礼しちゃいますぅ。せっかくぅ、言葉が通じるようにしてあげましたのにぃ」
目の前の少女は怒っているわりには妙に間延びした口調でそう言い返してきた。
「え……アレ……?本当だ。言葉、分かってる……」
「まぁ、私もぉ、異世界人の生体情報を操作したのはぁ、初めてでしたのでぇ、結果的に少〜し乱暴になってしまたかもぉ、知れませんがぁ……」
少女はひどくのんびりした口調でさらりと不穏なことを言い放つ。
「は!?あんた、俺に一体何したんだ!?」
「……それにしてもぉ……異世界人と言っても、見た目は私たちとそれほど変わらないのですねぇ……。興味深いですぅ……。まったく、こんな面白そうなことを私抜きでやるなんて、ひどいですぅ」
少女は俺の疑問をあっさり無視し勝手に言いたいことを言うと、俺との会話は終了したとばかりに例の美姫を振り返った。
「ごめんなさい、リィサ姫。こちらにもいろいろと事情がありましたの。今回のお礼は後ほど必ずさせていただきますわ。それと、この件は当面の間はご内密にお願いします」
例の美姫が恐縮したように頭を下げる。そのセリフに俺は思わず驚愕の声を上げていた。
「は!?姫!?あんたが!?そっちの美少女の方じゃなくて!?」
「え……っ、そ、そんな……美少女だなんて……っ、いきなり何を仰るんですの……っ!」
驚きのあまりダダ漏れになった俺の本音に、例の美姫が顔を真っ赤に染めて恥じらう。自分が何を発言してしまったのかに気づき、俺もかーっと顔に血が昇ってくるのを感じた。
「オヤオヤ、出逢ったばかりの異性にいきなりそんなアプローチをするとは、若いってイイですねぇ」
美姫の隣の男がニヤニヤした顔でそんな言葉をつぶやいているのも、俺の羞恥心に拍車をかけた。
「えぇ。私は姫ですしぃ、そちらの“美少女”さんも姫ですよぉ。ただ、国は違いますけどねぇ。私は隣国リーストの姫、リィサ・ロッテ・リーストと申しますぅ。姫らしい格好をしていないのはぁ、国家予算の節約のためと、ドレスだと研究に不向きだからなのですぅ」
少女、もといリィサ姫が相変わらずのマイペースで説明してくる。
「あ、あぁ、そっか……どっちも姫なのか……なるほどな」
俺はさっきの失言を何とか無かったことにしようと、誤魔化すように大きめの声でそう言って何度もうなずく。
「あのぉ、用も済んだようですし、私はこれで失礼してもぉ、よろしいでしょうかぁ?さっきついでに“記録”した彼のデータを詳しく解析していきたいのでぇ……」
「ええ。ご協力感謝いたしますわ、リィサ姫。帰りはまた私の瞬間移動でお送りします」
「いいえぇ、それは丁重にお断りさせていただきますぅ。貴女の空間操作は心臓に悪いのでぇ、緊急時以外は利用したくないのですぅ。と言うよりぃ、今後また今のような不都合があった際にぃ、再度呼び出されることを考えますとぉ、しばらくはここにいた方が良いと思うのですぅ。界聖宮のお部屋を一部屋貸していただきたいのですぅ」
「『心臓に悪い』……ですか……」
リィサ姫の言葉にショックを受けたように、例の美姫が美しい眉毛を八の字に曲げる。
「では、お部屋の手配は私がいたしましょう。リィサ姫様、どうぞこちらへ。君は、彼に事情説明を」
美姫の隣にいた男が、笑いをこらえているような表情でリィサ姫に歩み寄っていく。
「分かりましたわ、叔父様」
(……あの人、姫様の叔父さんだったのか)
リィサ姫を伴って建物の方へ消えていく男を見送り、俺は改めて美姫に向き直る。美姫はどことなく緊張したような面持ちで、真っ直ぐに俺を見つめていた。
目と目が合ったまま、だが第一声に何と言葉を発したら良いのか分からず、むしろうかつに声を出そうものならヘンに裏返った声が出てしまいそうな気がするほど俺自身も緊張して、しばらくの間、気まずいような、でも妙に胸が高鳴るような不思議な沈黙が続いた。
やがて、意を決したように美姫が唇を開く。
「あの……私、フロレンシア・フロラリア・リ・フレイン王国第一王女フローラ・アンリエット・ジョゼファ・ロザリーヌ・フレインと申します」
「え……?今、何て……?」
その、思わず漏らしてしまった我ながら間抜けな疑問の声が、俺の彼女に対する第一声となってしまった。
やんごとなき身分の人の名というのは、なぜこうも長ったらしいものなのか。その自己紹介は、俺にはまるで呪文か早口言葉を唱えているようにしか聞こえなかったのだ。
「……ってか、どこまでが国名でどこからが名前だった……?つーか、ファースト・ネームどれ!?」
「あの……フロレンシア・フロラリア・リ・フレインが国名で、私の名は、その……フローラ、とお呼びいただければ……」
軽くパニック状態の俺に助け舟を出すように、彼女が優しくそう申し出てくれる。
「そ、そっか、フ、フローラ……」
やっとのことで認識できた、その理想の眉毛の持ち主の名を、俺はドキドキしながら口にした。
よくよく考えれば、いくら本人から「フローラと呼んで」と言われようと、相手は一国の王女なのだから何らかの敬称をつけるべきだったのだろう。だが、当時の俺の頭にそんな考えは浮かばなかった。
「はい……。フローラ、ですわ」
他人から呼び捨てにされることに慣れていないのか、フローラは少し戸惑いの表情を浮かべ、ほんのり頬を染めた。はにかんだ顔で見つめ合って数秒、フローラは微笑んで再び唇を開いた。
「あなたのお名前は何と仰るのですか?」
「ああ、俺の名前は、た……」
言いかけ、俺はハッと口を噤んだ。
(ちょっと待て、俺。ここで俺の『高橋 光太郎』とか言う平凡極まりない名を名乗るのか!?しかも、フローラ・アンリエットなんちゃらフレインとかいう、やたら立派そうな名前の相手に!……いや無いだろ。世界を救うために召喚された勇者の名がタカハシ・コウタロウは無いだろ!)
自慢ではないが、俺はゲームの主人公に自分の名前をつけたことが一度もない。中世ヨーロッパ風だったり近未来SF風だったりする世界観の中に自分の名前が入った時の違和感を考えると何だか萎えるし、文字数制限などあった日には『勇者こうたろ』などという中途半端な名前になり、非常に情けなくも物悲しい思いをするからだ。
だから勇者の名前にはいつも、その時その時で一番カッコイイと思う横文字名前を適当に付けていたのだが……。
(うん、大丈夫だ。この世界に知り合いがいない以上、偽名を使ったところでバレる要素がない。しかし、悩むな……。下手したらこの世界の伝説になるかも知れん名だからな。……『アルス』じゃテンプレ過ぎるし……『アルデバラン』……はラスボスくさいし……)
頭にアの付く名前を片っ端から思い浮かべていた俺の脳裏に、その時ふっとある名前が閃いた。
「……アーデルハイド」
「え……?」
「俺の名は、アーデルハイド。アーデルハイド・タカハシ・コータローだ」
ふと頭に閃いて、うっかりカッコイイなどと思ってしまったその名が、アルプスの山小屋でおじいさんとヤギたちに囲まれて暮らす例の少女の本名であることを思い出すのは、これから数ヶ月後のことになる。
「気軽に『ハイド』と略してくれてもいいぞ!」
ドヤ顔でそう言い放つ俺の頭を、時間を遡ってはたいてやりたいものだが、そういうわけにもいかず、この時点で俺のこの世界での名は確定してしまった。
「アーデルハイド様……。聞いたことのない響きですわ……。でも、どこか高貴な感じのする素敵なお名前ですね」
この時は会心のネーミングだと思っていた“自分の名前”を理想の眉毛の美少女に褒められて、俺は“鼻高々”を可視化できたなら50cmくらいは鼻が伸びていただろうというくらいの上機嫌でうなずいた。
「……で、この世界には今どんな危機が起きてるんだ?異世界から勇者を召喚しようだなんて、相当な事態が起きてるんだろう?」
わくわくしながら俺はフローラに尋ねた。
平和ボケとすら言われる現代日本のごくごく平均的な庶民の家に生まれ、剣の修行はおろか武術・体術の心得など一切なかった当時の俺が、何を根拠に異世界を救えるつもりでいたのか、今の俺にはさっぱりなのだが、恐らくはこれが俗に言う“若さゆえのアヤマチ”というヤツなのだろう。その軽いノリでの発言が、後にどんな事態を引き起こすことになるかも知らずに……。
「まぁ!アーデルハイド様は勇者でいらっしゃるのですか!?」
驚きのためか、フローラの美麗眉毛がピョコンと跳ねる。
「え……?まぁ、その……勇者……って言うか、これから勇者になる予定と言うか……。……ってか、この世界を救うための“勇者”として呼び出されたわけじゃないのか!?俺!」
フローラの反応に雲行きの怪しさを感じ、俺は胸に不安を過ぎらせつつ問う。するとフローラは困惑したように美しい眉を寄せて俺を見た。
「……いいえ。この世界に現在、勇者を必要とするような差し迫った危機はございませんわ」
「はぁ!?じゃあ何で俺、ここにいるんだ!?何であんな恐怖体験までしてこの世界に召喚されたんだ!?」
その瞬間、フローラの目が泳いだのを俺は見逃さなかった。
言い訳を探すかのようなしばしの沈黙を一国の王女らしい堂々とした微笑みでやり過ごした後、フローラはきっぱりとこう言い放った。
「この世界の学術の発展のためですわ!」
「……………………は?」
「この世界の他にもう一つ、この世界とよく似た別世界が存在するということは、遥かなる昔から言い伝えられて参りましたの。けれど、それを証明する手立ては無く、それが真実なのか、空想に過ぎないのかは長年議論の的となっていたのですわ。ですがつい最近、私の叔父である界聖宮長が思いついたのです。私の空間を操る能力を“応用”すれば、この世界と異世界とを“つなげる”ことが可能なのではないかと……。そうして幾度かの試行錯誤の結果、私はついにこの世界の歴史上初めて、世界と世界を結ぶことに成功しましたの。けれど、私のこの身体全体をあちら側の世界へ渡らせることは現状まだ不可能で、腕一本を出すので精一杯だったのですわ。それでもその腕を使い、手に触れたものをこちら側へ引っ張り込み、あちら側の世界にどのような動植物が存在するのか、どのような世界なのかを少しずつ解明してきたのです。これまでは草花や小石や小動物がせいぜいで、向こう側の世界に私たちのような知的生命体が存在するのかどうかも分からずにいましたわ。けれど今日、ついに向こう側の世界にも私たちと同じような“人間”が存在していることが証明されたのです……!」
淀みなく流れる川のようにさらさらと、時に情熱を帯びたような声音でフローラは言葉を紡ぐ。俺はその説明を呆然と聞いていた。
そのあまりに堂々とした説明っぷりに一瞬、誤魔化されそうになる。だが俺は話の核心を聞き逃しはしなかった。
「それって、つまりアレか……?俺は地球に人間がいるかいないかを証明するための証拠物件ってことか?もしくは標本採集的に集められた“地球の生物サンプルその1”ってことか……!?」
「そんな……!違いますわ!貴方は単なる証拠物件や生物標本などではなく、あちらの世界を知るための“生きた資料”なのですわ!」
「ソレ、結局同じことじゃんか……」
俺は脱力し、ふらふらとその場に座り込んだ。ガッカリがひど過ぎて、心なしか目眩までするような気がする。
「何だよー。せっかく異世界に召喚されて勇者として大活躍できると思ったら、ただの研究資料扱いかよー……」
「ご期待に添えず申し訳ありません。けれど、こちらの都合でこのように強引においでいただいた以上、できる限りのおもてなしをさせていただきますわ」
「おもてなし!?」
その一言に俺は瞬時に反応して飛び起きた。
(おいおい、これってひょっとして、かなりオイシイ話なんじゃないのか!?タダで異世界ツアーできる上に、地球のことを話して聞かせるだけで、一国の王女、しかもこんな美麗眉毛の美少女が“おもてなし”してくれるとか)
俺は改めてフローラを見つめる。その眉は変わらず、夢でも想像できなかったような理想の形で俺を魅了していた。
(イイじゃん。こんな“理想の相手”に出会えるチャンスなんて、この先あるかどうか分からないじゃん。だったらしばらく堪能しとけばいいじゃん?)
俺はその眉に見惚れたまま、自然と首をタテに振っていた。
「いいよ。その研究資料だか学術の発展だかに、つき合ってやるよ」
「本当ですの!?」
フローラが瞳を輝かせて歩み寄って来る。
「ありがとうございます!この国の王女として最大級の感謝を捧げますわ!」
言いながら、フローラは両手で俺の手を握り、上下に振った。
最初に握った時にはろくに味わう暇も無かったその感触に、急に心臓が暴れ出したかのような動悸を覚える。
(女子の手って、柔らけぇ……っ、てか、近い……。こんなに女子と接近したの、いつ振りだよ、俺……)
「い、い、い、いやぁー、た、大したことじゃな、ないってー……」
全身、特に手のひらのあたりからヘンな汗が大量に噴き出しそうな気がして、俺はさりげなくフローラの両手から俺の手を脱出させた。
(う……っ、何か、心臓が疲れそうな予感……。大丈夫か?俺……)
 この時の俺はまだ予想もしていなかった。
この時点ではまだ勇者を必要としていない、まるで静かに凪いだ水面のように穏やかな世界に、異世界の人間という“異分子”が小石のごとく投げ込まれたことにより巻き起こる“波紋”を。
そして、じわじわと広がるその波紋が、やがて大きな波乱となり、この世界を、そして俺とフローラを巻き込んでいくことを。
だが、まだこの時俺が感じていたのは、早摘み苺のように甘酸っぱい初恋の予感だけだった。
これが、俺が彼女と、彼女の住むセカイに出逢ったハジマリの日。
そして後に不本意にも“英雄王アーデルハイド”などと呼ばれることになる“俺”の始まりの物語なのである。
|