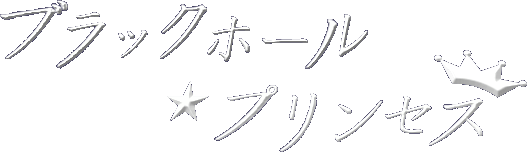
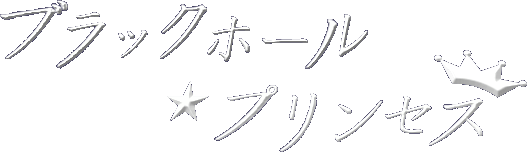
言ノ葉ノ森TOP>INDEX(もくじ)>シンプルINDEX>第2話(イマココ)
「あのさ、フローラ……頼みがあるんだけど……」
リィサ姫と二人で事情を説明すると、フローラは驚いた顔をした後、同情するようにその形良い眉を寄せた。
「まぁ!重力が違うだなんて……。さぞご不便をお感じになったことでしょう。今まで気づかずにいて申し訳ありません」
「あ、いや……気づかなかったのは俺も同じだし……」
さっきのリィサ姫の発言を引きずったままの俺は、フローラの謝罪にすらビクビクして声が小さくなる。
「では早速、重力調整させていただきますわ。範囲はアーデルハイド様のお手の届く範囲を基準に設定させていただくとして……重力の方は……どれくらいにしたらよろしいのでしょうか?」
「生体データからではぁ、そこまでは分かりませんからねぇ……。そもそも重力なんてぇ同じ惑星の上であってもぉ、微妙に違いがあるものですぅ。ここは実際に少しずつ重力を上げていってぇ、アーデルハイド様に自らの感覚で選んでもらうのがぁ良いと思いますぅ……」
「そうですわね。では……」
言いながら、フローラがチョーカーの聖玉に指を触れる。
直後、ジェットコースターで垂直落下したような、あるいはとんでもなく重い物体を身体の上に載せられたかのような感覚が襲い、俺はそのまま地面に突っ伏した。
「ぐぇ……っ。フ、フローラ……っ、ちょ……っ、お、重過ぎ……」
「きゃあぁあっ!すみません!いきなり重力を重くし過ぎましたわ!!」
フローラはあわてふためき、再び聖玉に指を触れる。
途端、圧迫感はフッと消え去った……と思ったら、今度は身体がどんどん軽くなっていき……とうとうフワリと地面から浮き上がった。
「ちょ……っ!フローラ!浮いてる!身体浮いてる!」
「きゃあぁぁっ!すみません!今度は軽くし過ぎましたわ!」
この俺たちの騒動に、広場の人々もさすがに気づいてざわつき始める。
「オイ……アレって……フローラ姫様が聖玉をお使いになってるんじゃ……」
「嘘だろ!?一難去ったと思ったら、すぐにまた大ピンチかよ!?」
「誰だよ!?あのコントロールが致命的にド下手な姫様に聖玉を使わせた奴は!?」
その声は否応なしに俺の耳に入って来て、俺はおぼろげながら事態を悟り始めていた。
――そう。フローラは歴代聖玉姫の中でも1、2を争う強い能力を持っている。
だが、そのあまりの強力さゆえに2、3回に1回の割合で聖玉のコントロールを失敗してしまうという「それ、何てロシアン・ルーレット?」と訊きたくなるような致命的な欠点を抱えているのだ。
「ぐへぇ……っ!」
再び重くなり過ぎた重力によって空中から地面に叩きつけられた俺は、情けない悲鳴を上げながら石畳の上に這いつくばった。
だが、事態はそれだけでは終わらなかった。
「あら?あららら?ど、どうしましょう……っ!聖玉の制御が利きませんわ……!」
フローラの首元で聖玉が妖しく明滅しだす。
「た、退避だ!総員、広場の外へ退避ぃーっ!!」
先ほどの聖宮騎士団長が広場中に響き渡るような声で叫び、住民たちはフローラから少しでも距離をとろうとするように一斉に駆け出した。
「え……ちょ……っ、俺、動けな……っ、逃げらんね……っ」
「あらあらぁ……運が悪かったですねぇ……ご愁傷様ですぅ」
重い頭を何とか上向かせ見上げると、この事態の元凶の一人であるリィサが聖玉の影響が及ばない安全圏――すなわちフローラのすぐそばに、ちゃっかり避難しているのが目に入った。
「ちょ……っ、コラ……っ、助け……っ」
そのうちに俺の視界の中で、広場の風景がぐにゃりと奇妙に歪み始めた。
まるで周囲の景色を360度プリントした布を、少しずつ引っ張って絞り上げていくように……。
(あ……、めっちゃ既視感が……。これって、俺がこの世界に召喚された時の……)
まるで恐ろしい吸引力を持つ掃除機に無理矢理吸い込まれていくように、景色の歪みの中心へ向かって身体がずるずると引っ張られていく。
必死に踏ん張ろうとするが、無駄だった。
「アーデルハイド様っ!」
心もち地上数センチくらい宙に浮きながら歪みの中心へ吸い込まれていく俺に、フローラが手を伸ばす。
俺もフローラへ向け手を伸ばそうとする、が……その手は彼女にかすりもしなかった。そのまま、俺は足先からゆっくりと歪みに呑み込まれていく。
吸い込まれる瞬間、周りの景色が何故かスローモーションのようにゆっくりになって見えた。
そしていつもより感覚の鋭くなった耳に、避難する住民たちの声が飛び込んでくる。
「いやー、久々だな。姫様の大暴走」
「いっくら美人でもコレがあるからなー。恐ろしくって、とてもおそばにゃ寄れねぇよ」
「それにしてもあの勇者様、マジ勇者だったな。姫様に近づけば近づくほど、アレに巻き込まれるリスクも高くなるってのに。マジ、勇気あるよ。……惜しいお方を亡くしたもんだ」
(“勇者”って、そういう意味だったんかい!……ってか、勝手にヒトに死亡フラグ立ててんじゃねぇ……っ!)
その文句は口から発せられることなく、俺の視界はブラックアウトした。
その後はやはり身に覚えありまくりの阿鼻叫喚の世界だった。
何かに足先を引っ張られ、身体を粘土のように“みょーん”と引き伸ばされているような感覚の中、俺は一瞬『あ、やっぱ俺、死んだかも』と思った。